こんにちは若しくはこんばんは。
綿谷です。
今回は、私が試験勉強を行う際に使った教材や、試験勉強のやり方などをお伝えする記事となっております。
長くなるので分割した方が良いかなと思いましたが、纏めて説明した方が流れで分かりやすいかなと思いますので、ノンストップで行かせてもらいます。
教材
先ず初めに使用教材ですが、当時の私は以下の物を使用いたしました。
基本テキスト:みんなが欲しかった!行政書士の教科書(TAC出版)
問題集:みんなが欲しかった! 行政書士の問題集(TAC出版)
行政書士 過去問 2024(Trips LLC)
記述対策:みんなが欲しかった! 行政書士の40字記述式問題集(TAC出版)
以上です。
TACの回しもんかテメェ…?と言わんがばかりのTAC尽くしですが、別にそういうわけではないです。
これ等を選択した理由はただ一つで、図が分かりやすいという点です。
これは個人差もありますが、人間結局活字だけだと中々頭で理解しづらいんですよね。
図のような視覚情報がないと、どうにも理解が深まらないといいますか、本当にこの認識で合ってんのかなと…。それに、活字の情報だけで整理して、自分で図を作ろうにも、その図が合ってるのかもちょいと微妙。
何故なら活字の時点で前述した問題点があるから…といったように、図があるというのは非常に重要です。
勿論「活字で余裕ですけど?」みたいな豪の者は関係ないのでしょうが、世の中にそんな活字適合者が多いとは私自身到底思えません。
その為、幾つか本屋で教科書をパラ見してきた私的に一番図が多く、図の解説もそこそこ充実していた上記の物を使用いたしました。とはいえ、これは個人的な感想ですので、あまり鵜吞みにせず、吟味していただきたいです。因みに基本テキスト選びのコツは民法の相続や取得時効ら辺の解説ページを見ることをお勧めします。
あそこらへん初見だと結構ややこしいので、パラ見してなんとなくわかった気がするってなった物はもしかしたら結構他の解説も分かりやすかったりするので…。
あと、もう一つ注意点があります。内容についてですが、主要科目の民法と行政法(あと憲法も)はどの教材も言うほど大差ないのです。しかし、基礎法学や会社法、商法についてはテキストによってボリューム変わったりするので確認を怠らないでください。配点が少ないとはいえ、案外それに助けられたりボッコボコにされたりしますので。因みに私は商法と基礎法学全落としで普通に不合格を確信してました。(なんとかなりましたが)
また、他にも判例集や重要論点集などもありますが、ぶっちゃけこれは欲しい人は買えばいいんじゃないかなという感じです。少なくとも私は判例はネットで調べてましたし、重要論点も「いや重要じゃないとこなくない?」の精神で基本テキスト回してただけですがなんとかなりました。
続いて問題集ですが、取り合えず問題集はこの二つを滅茶苦茶回すことです。
特に後者の”行政書士 過去問 2024(Trips LLC)”は無料のスマホアプリで、過去問オンリーですので、一々ネットで過去問調べる手間が多少減りました。
過去問は兎に角回せ
それに限ります。
他の問題集も追加購入しても良いですが、ぶっちゃけ手が回りませんし、大体内容も過去問主軸なことに変わりはないです。ただ、記述問題はこの二つでは少々物足りませんし、苦手な人は最後に挙げた”みんなが欲しかった! 行政書士の40字記述式問題集(TAC出版)”を購入して進めるといいでしょう。私は記述のおかげでなんとか生き延びた人間ですので、記述対策はちゃんとしておけと言っておきます。
勿論「無くても記述余裕だわwwww」みたいな人も一定層ネットで見かけましたが、結構稀な例ですので余程自信がある方以外はマージン取ってちゃんと対策しておいた方がいいです。
有った方が楽な物
六法です。
ポケットでも全書でも昔のでも良いから持ってたら多少楽になります。
最近の基本テキストは、私が挙げた物含め、ミニ六法が付属しています。
勿論これらは非常に使えるのですが、要所要所省かれている条文があったりします。
しかも、そういうところに限って択一や記述で出てきたりします。
ネットでも法令検索のサイトが有りますが、付箋とか付けれないので紙であった方が便利です。
一応コピー機で該当箇所を印刷という手もありますが、昨今コピー機を持ってない方もいらっしゃると思いますので、ポケット六法買っといたら後々楽です。
因みに私は大学時代に使用していた有斐閣さんのポケット六法を使用しました。
案外これ、過去問アプリだけで別の法律資格取ろうとする時とかにも使えるんですよね。
勉強時間
これから話すのは独学一年無職しながら資格を取った私のやり方ですので、参考になる部分とならない部分があると思います。
ですが、正直内容的には働きながらでもできる内容と考えましたので、共有させていただきます。
先ず基本的な勉強の仕方ですが、最も重要なのは時間配分です。
これは大学受験の時と同じ配分で行い、無事成功したものですので、個人的には最も自分に合っている配分とも言えます。
30分ごとに5分~10分休憩
1時間後ごとに休憩(時間は決めない)
一日3時間
「お前勉強嘗めてんの?」そうお思いの方もいらっしゃると思いますが、少なくとも私は一年これやって合格しました。
なんなら、大学受験時代は一日4時間でしたが、同じ手法で無事志望校に合格できました。今からひとつひとつ解説していきます。
“30分ごとに5分~10分休憩“
先ず前提というか個人的に深く納得した説に「15・45・90の法則」というものがございまして、ざっくり言うと人間そんなに集中できる時間長くないよねみたいな物です。
これに少し持論を加え、私は人の集中できる時間は連続30分、休憩挟んでも1時間と考えてます。そもそも、小中学校の授業が凡そ1時間区切りの時点というのもこの持論の根拠になっております。
加えて私はそこまで体力がありませんので、連続でも人の半分くらいしかやる気続かなそうと考えた末に生み出した配分です。
総勉強時間は幾らでも伸ばしてもいいですが、”30分ごとに5分~10分休憩“と”1時間後ごとに休憩(時間は決めない)“だけは忘れないようにしましょう。
“1時間後ごとに休憩(時間は決めない)“
これは前述した「人の集中できる時間は連続30分、休憩挟んでも1時間」という持論に関するものですが、5分~10分程度の休憩なんて気休めにしかなりません。ですから、しっかり脳をリフレッシュする時間が必要なのです。しかし、「〇時まで休憩する!」と考えたまましっかり休めるでしょうか?私はやる事があると気になってしっかり休めない所謂”夏休みの宿題出されたその日に終わらせるタイプ”の子供でしたので、無理です。ですので、敢えて勉強のことを忘れてください。
寧ろ勉強のために忘れてください。
その内やらなさ過ぎて「やっべやらなきゃ」と自主的に勉強する意欲が湧きます。特に、私と同じタイプであるならば。
やらなきゃいけないからやる勉強とやろうと思ってやる勉強は全く違います。
後者は特にパワーが違います。何しろ学習に前のめりになり、貪欲になりますから。
“一日3時間“
こちらに関してはぶっちゃけ匙加減です。
何なら、私は7月のLEC模試でボコボコにされるまでは一日2時間しかしてませんでした。
前述の一時間ごとの休憩の配分が滅茶苦茶上手い人は、多分1時間ごとに休憩を〆て勉強再開とかできると思いますし、それが難しい人や純粋に時間ない人は一日2時間とかになるとかもしれません。
ただ注意してほしいのは、少なくとも1時間以上はすることだけです。
これは模試を受けた日などは別にやらなくてもいいですが、少なくとも何らかの教材に毎日触れてください。
土日は勉強休みとかでもいいですが、その分どこかで2時間以上やるとか30分増やすとかでもいいですが、できることなら一時間でも毎日教材に必ず目を通す。これは心にとめておいてください。
とはいえ、やる気が有り余ってる場合は寧ろ止めない方が良いです。
上記のやり方は勉強が嫌いor飽きてきた方向けのやり方ですので、やる気に満ち溢れている方は勢いのまま続ける方が吉です。
勉強方法
次に勉強方法ですが、最初に言うことは模試は三回以上受けてくださいということです。
はっきり言いますが、過去問で高得点取れたからって天狗になってたら模試でボコボコにされます。
そして本試験も模試くらいにはボコボコにしてきます。
そりゃそうですよね、過去問で勉強してるんだから過去問解いたら高得点取れますよ。
そのため、一先ずは過去問で天狗になれるレベルまで行けた方法を踏まえ、試験後に追加でやったものを混ぜ合わせた勉強方法をお伝えします。
また、私が受験した模擬試験も紹介しておきます。
以下は私のスケジュールに合わせた物ですので、皆さんは自分に合った模試と回数をお選びください。
1回目:到達度確認模試【第2回】(LEC)
2回目:全日本行政書士公開模試【第2回】(LEC)
3回目:ファイナル模試【第1回】(LEC)
勉強のフロー
- 基本テキスト(1週目)
- 何の線も付箋も張らず、只々読み込む(コラムや注釈は後回し)
- 問題集(1週目)
- 間違えた問題には付箋を貼り、解説の重要な語句(間違えた語句等)にマーカーを引く
- 基本テキスト(2週目)
- 今度はコラムと注釈込みで読み込み、条文の重要語句(特に行政法の要件等)などにマーカー等で線を引く。出てきた条文は付属の六法で探し、要件等をマークしておく。表には名付けした付箋を貼る。
- 問題集(2週目)
- 間違えた問題を先にやる。その後、全体を回して、1週目と同じく間違えた問題に付箋を貼る。
- 過去問(1周目)
- アプリの過去問を1年分試験と同じ時間で解く。
終了後は間違えた問題を解きなおす他、出てきた判例や条文を調べておく。
- 基本テキスト(3週目)
- 問題集や過去問で間違えた問題を重点的に再確認。
- 以下ループ
- 問題集(2週目)~基本テキスト(3週目)をループ。
・過去問に模試の問題を含む。
・偶にある資格学校の無料講座で苦手分野の物があれば受けておく。
(特に一般教養とか行政処分とか)
受けたい講座が無ければ、取り合えず有名な行政処分と違憲判例だけは調べておく。
(大体試験まで残り数か月になると、資格学校は受講生以外にも無料講座開いてくれるので)
また、問題集や基本テキストは最初のうちはやるページ数ある程度決めておいた方が良いです。
私の場合は以下の通りで進めました。
基本テキスト:20ページ
問題集等:10ページ
少々少ないと思われる方は、各自調整していただいて結構です。
私自身、2週目以降は1単元ごとにしていましたし、前項でも言った通り、やる気が有り余ってる場合は寧ろ決めない方が滅茶苦茶進みます。
ただ、過去問だけは絶対に通してやり切ってください。
トイレ休憩などは問題ないですが、がっつり休憩したら「それ別に普通に問題集解くのとと変わんなくない?」ということですので。そもそも、過去問をやる理由は、少しでも本試験と同じ環境を味わうという為の物と私は考えております。「模擬試験受けまくればええやん」という意見もありますが、皆が皆そうできるわけではないので。あと単純に、長時間の脳の酷使に慣れとかないと本試験で頭疲れて苦しいです。
〆
いかがでしたでしょうか。
私が昨年行った全てを余すことなく詰め込みましたが、伝えきれましたでしょうか。
当時の私も色んな勉強法サイトを拝見し、色々と参考にさせていただいたものです。
私も同じように誰かのお力になることができましたら幸いです。
最後に、何時の世も論争が起きているイメージのある”質”か”量”か論争に対しての私的な意見を述べて、それを〆の言葉とさせていただきます。
個人的には、”質”が無いければ”量”をこなしても効果は薄いですが、”量”が無ければ”質”があってもインプットしきれないと考えております。
ただ、”質”は良過ぎてもそこまで悪影響は無いですが、”量”が多過ぎると精神的にも身体的にも支障をきたします。無理の無いほどほどの”量”で“質”の高い勉強を目指しましょう。
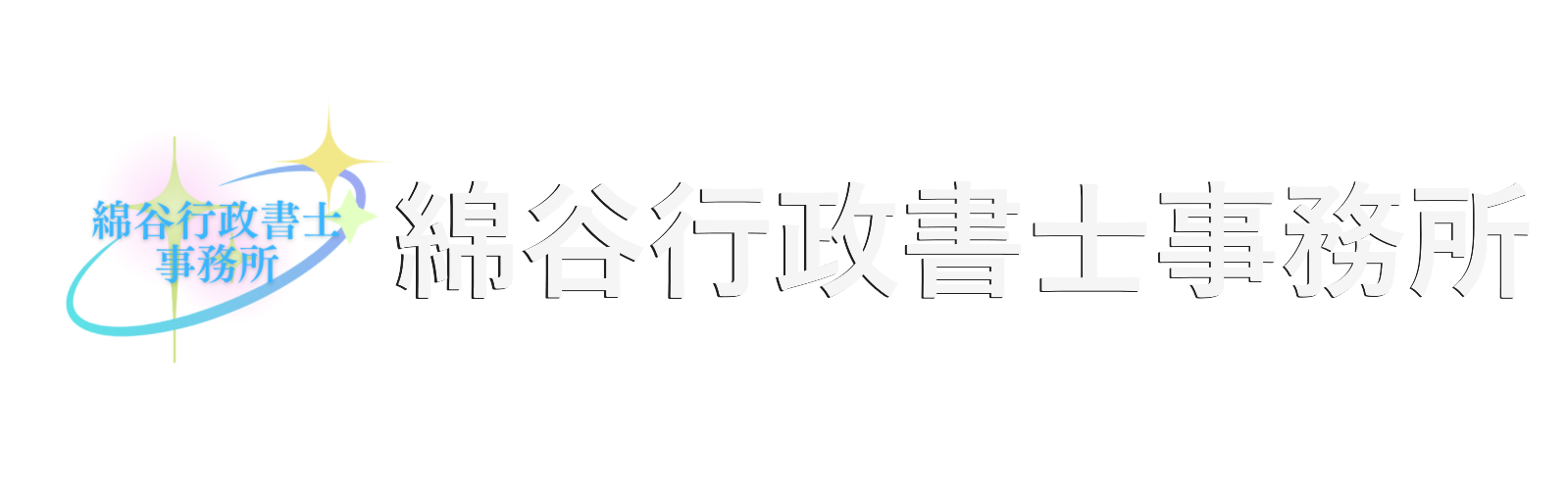
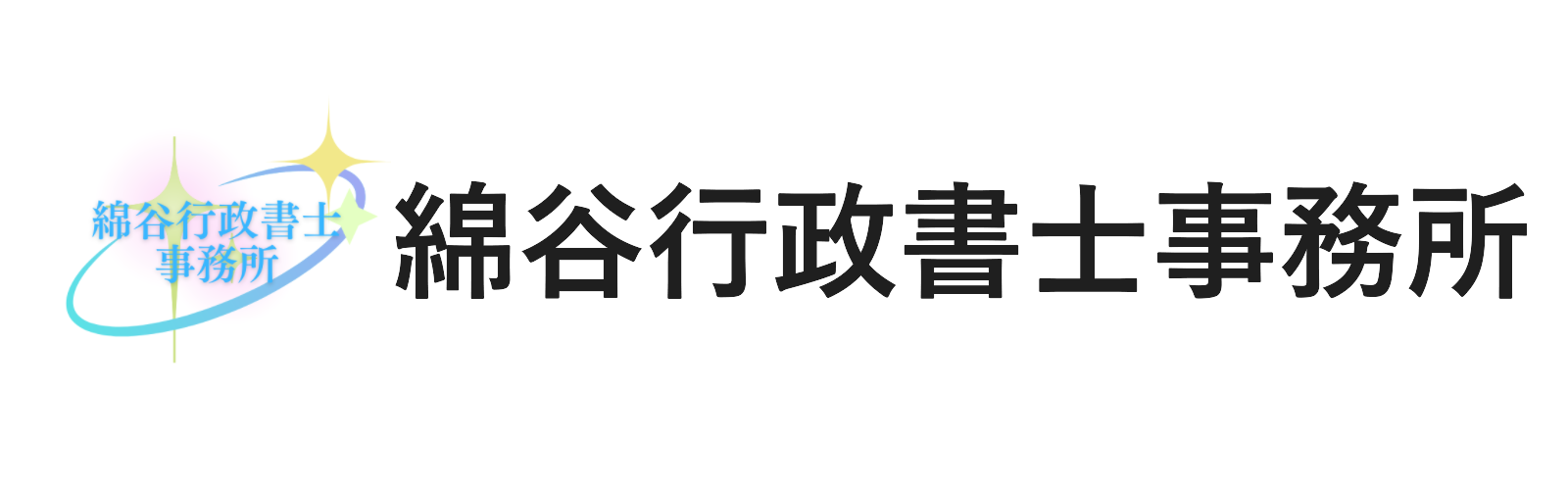
No responses yet